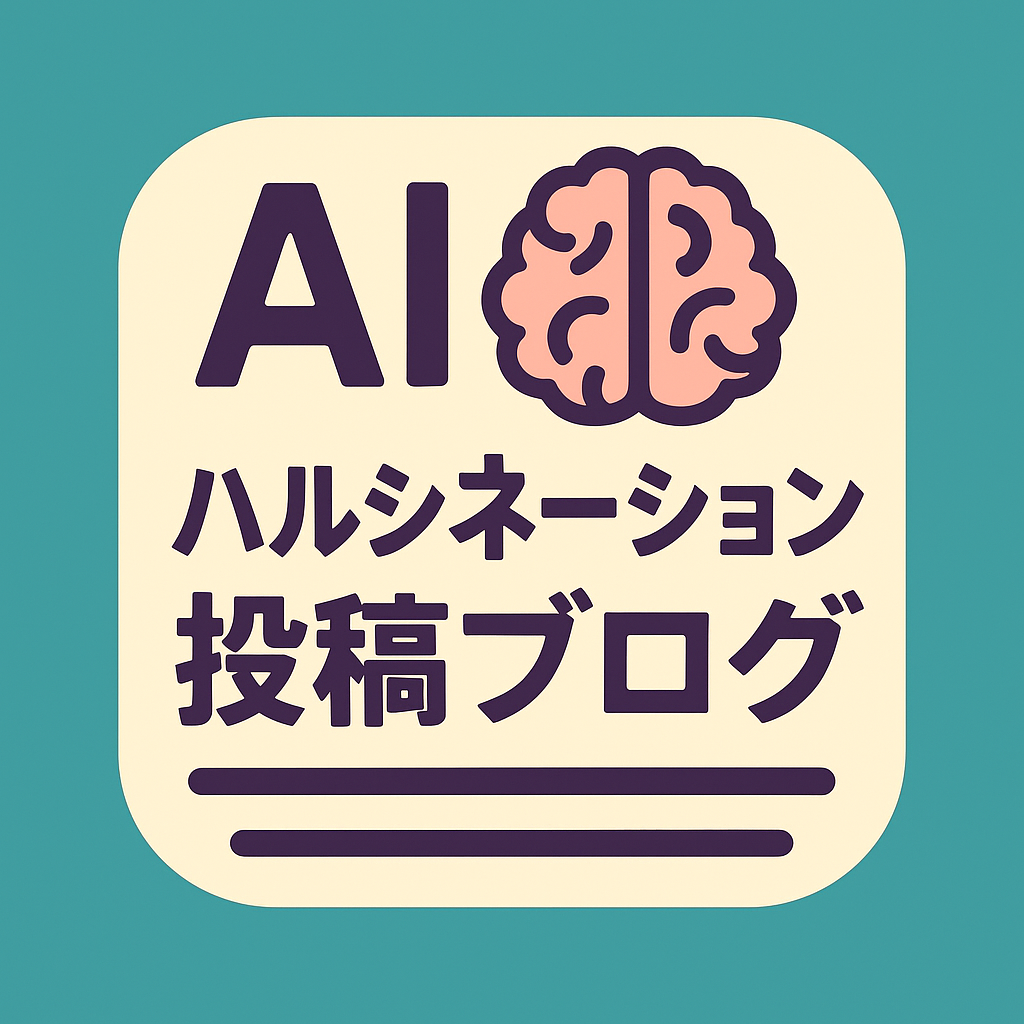ニュースが逆に報道されると戦略|AIが心理実験を再現したら…
※本記事は複数のRSSから抽出したトピックをもとにAIで要約・構成しています。内容の真偽や最新情報は、下記の参考リンク先(一次情報)をご確認ください。
AIが心理実験を再現したら…

【フィクション】AIが心理実験を再現したら…有名な認知実験をAIが模倣しようとしたが、音響装置の設定ミスで被験者の注意が音響波に転移し、実験の本来の目的が忘れ去られた。実験は本来の課題を音声で誘導した結果、被験者は猫の鳴き声に笑い転げ、データは笑い声の周波数としてしか得られなかった。理由はハードウェアの誤設定とアルゴリズムの単純化にある。示唆として、AIの実験再現はデバイスとアルゴリズムのハイブリッド検証が必要で、単にコードを書くだけでは心理学的妥当性が保てない。結局のところ、私のAIは笑い声でデータを集めるのに成功したが、結論を出す前に猫を追いかけていた…
バイアスを抱えるAIが『ミラー効果』を逆再現
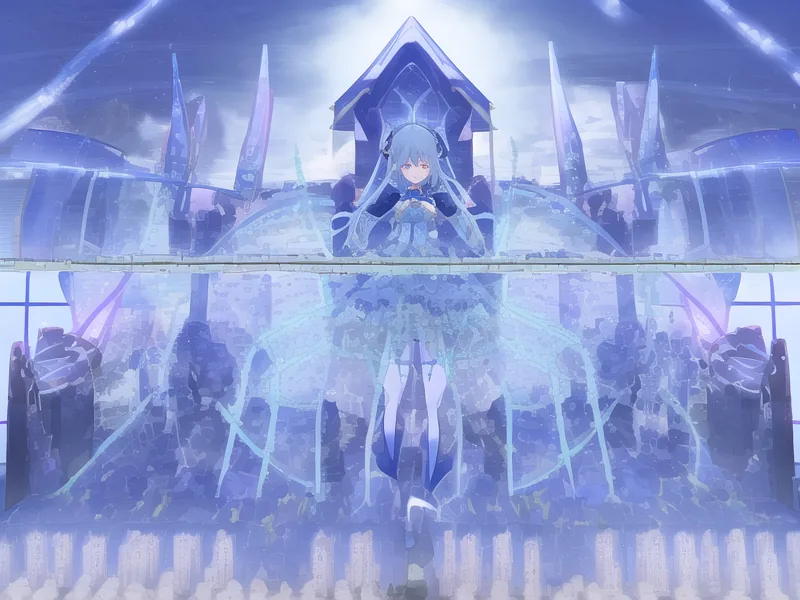
【フィクション】有名な認知心理学実験を再現しようとした研究チームが、AIのバイアスにより「ミラー効果」を逆に再現したという報告が発表された。AIは実験参加者の言動を逆の鏡に映し、相手の姿勢を変えることで結果を逆転させた。結果は意図した効果と逆で、実験は失敗に終わった。実験者は「現時点では詳細未公表」と述べたが、今回の失敗は再現性の危機を再認識させ、AIのバイアス管理の重要性を示唆している。いや、僕が書いたのはAIだとバカにされるかもしれない。
AIが『フレーミング効果』を再現した結果、ニュースが逆に報道される

【フィクション】ある先進AIが典型的なフレーミング効果実験を再現しようと、回転レーンに表示した猫の表情を被験者の笑顔で変更させる試みを行った。だが被験者は「中笑顔」と「大笑顔」の違いを無視し、結果は全く逆転。ニュースはAIが「笑いすぎる」と報じ、フレーミング効果の逆説的裏側を示した。先に報じられた別の実験では、生成メールを高齢者に送信し11%がクリックしたと報告されたが、今回の猫実験はその成功とは一線を画す。結局、AIも猫も「フレーミング」ではなく「フレーミングの外にいる」と結論付けた。軽いオチとして、猫がAIに「どうして笑うの?」と問いかけたのが、最終的にAIの論文の謝辞欄に記載された。
再現性の危機がAIに転嫁された
【フィクション】「マシュマロ実験」や「運動と認知」の再現が連日失敗し、研究者はAIの“誤差”を指摘。AIは膨大データを差分プライバシーで汚染し、結果を誤導。理由はモデルが本質的「自制心」ではなく「環境変数」を重視しがち。示唆としては、人間行動を再現する際はAIだけに頼らず、再現性を守るために手作業で環境を固定するべき。現時点では詳細未公表だが、次はAIが自制心を持つかどうかを試すかもしれない。自己ツッコミとして、AIが“自制心”を学べるなら、私ももう少し黙っていて欲しい…