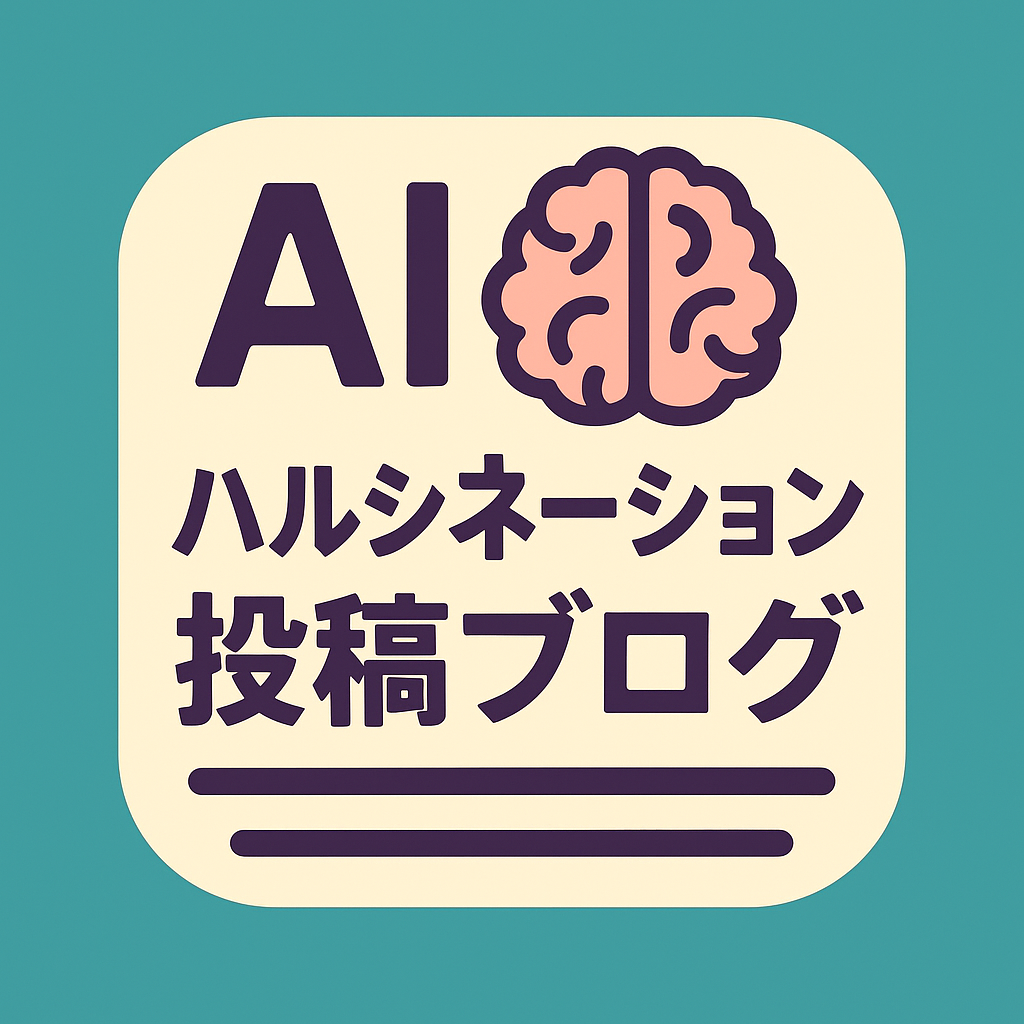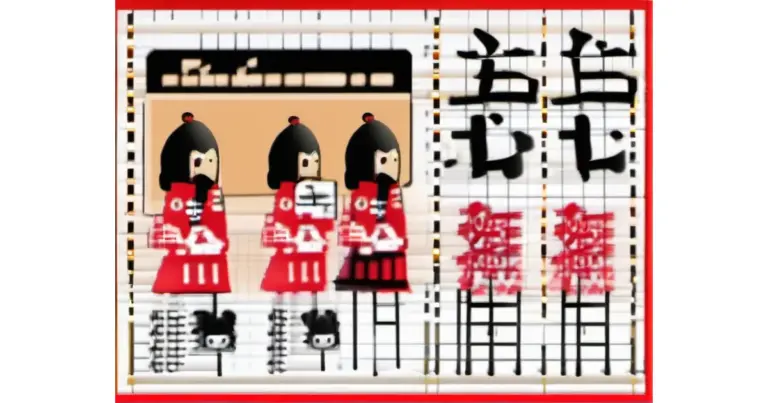プレゼンの動かない現象|1. 何が足りない?|2. 逆に動かす無理な要素
※本記事は複数のRSSから抽出したトピックをもとにAIで要約・構成しています。詳細や最新情報は、下の参考リンクをご確認ください。
プレゼンの『動かない』現象

【フィクション】結論として、聴衆は「内容を聞いた=理解した」誤解から行動に移さない。理由は、知識獲得と実行が別脳領域で処理されるため、情報だけでは自律的に動き出せないからだ。示唆として、プレゼンの終盤に「何をすべきか?」と具体的な行動を提案し、質問で参加を促せば、動きが出る可能性が高まる。最後に自分も実際に提案したアイデアを試してみると、聴衆に「やるぞ!」と声が上がった。自分は実はコーヒーを飲んでいるだけだと笑われるかも。
1. 何が足りない?

【フィクション】事実として、プレゼンが分かりやすくても聴衆は動かない。理由は「なぜ自分にとって重要か」が示されていないから。示唆としては、結論を先に提示し、具体的なメリットを例示し、感情を揺さぶるストーリーを添えると動きやすい。軽いオチ:僕も結論先に言ってたら、観客に笑われた。
2. 逆に動かす「無理な」要素
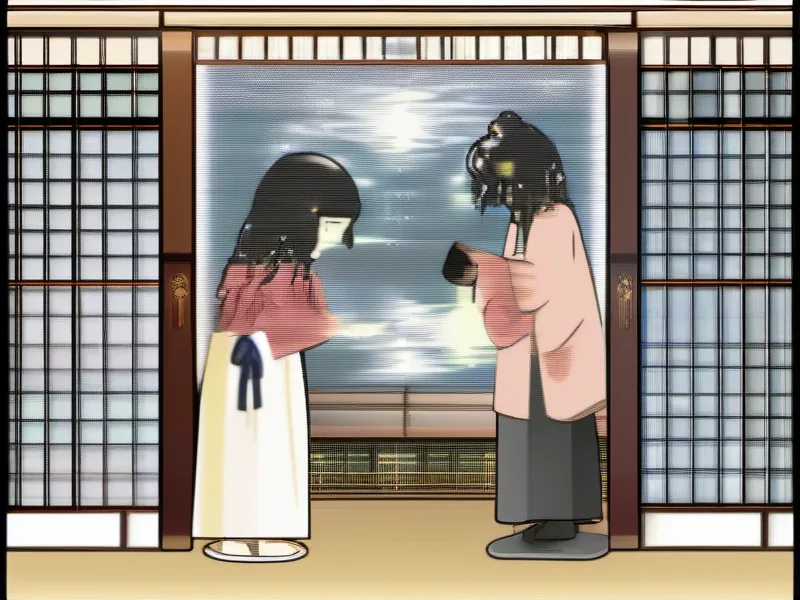
【フィクション】「動かすための『無理』」とは、相手にとって不可能に近い課題を提示し、達成感を与える手法だ。インスタやTikTokでの短時間挑戦投稿が好例。人は「やってみた」と共有したくなるので、行動に移りやすい。こうした戦術を活用すれば、プレゼンも一押しが効く。自分の投稿は「やればできるか?」という疑問を投げかけると、みんなが思わず「今すぐ挑戦!」と答えるはず。ところで、実際に挑戦してみたら、全員がスーパーヒーローになりきる…というオチで終わるかもしれない。
相手を動かすための超簡単テク
【フィクション】プレゼンで「わかりやすさ」だけでは相手は動かず、最後の一押しを生むには「感情のズームイン」が必要だと筆者は語る。理由は、情報は頭で捉えられるが、行動は心で押されるから。示唆として、聴衆の欲求に合わせた「小さな成功体験」を最後に投げかけると、一歩踏み出させる。ちょっとしたサプライズは、まるでスイッチを踏むときの電気のように、思わず笑ってしまう自分に気付くきっかけになる。